社員インタビュー
若手職員からベテランの職員まで、応募の経緯や仕事のやりがい、将来の目標、
また協同測量社の働く環境について生の声をご紹介します。

測量することで、
古い地図が更新されていく
達成感
T.Hさん
地理情報部 台帳システム課
新卒で入社してから4年間、地理情報部 台帳システム課に所属しています。市町村ごとに管理されている道路や上下水道に関する情報を更新して、台帳を作る仕事をしています。
たとえば、道路が一部拡張されたり、新しく家が建って下水道の管路がつながったりした際に、新しい情報を追加することになります。具体的な作業としては、現場で道路の形や、マンホール、付近の消火栓や側溝などの位置を測量したデータを、会社に戻って地理情報システムに入力して地図上に落とし込みます。そうすることで、道路や上下水道専用の台帳管理システムで、それぞれの情報を管理できるようになります。

普段、現場と社内での仕事の割合は半々くらいでしょうか。入社して初めての現場は、車で3時間ほど行った山の中でした。道路工事の調査だったのですが、昭和時代の古い地図しかなくて、現状と全然違うことに驚きました。1キロ以上という長い距離を測量して新しい図面を作りました。

各市町村からの依頼を受けて現地の調査をし、最終的にデータをまとめた報告書が完成した時には、一つひとつの仕事に達成感があります。自分たちの仕事で、古い地図が新しい地図に更新されることにやりがいを感じます。
私は長野市出身で、県内の専門学校で情報処理やプログラミングを学びました。学校の先輩が働いている協同測量社に会社見学に来て、山裾の住宅街という落ち着いた環境で、社員のみなさんがパソコンに向かって集中して仕事に専念している姿に好印象を持ちました。
地理情報部の先輩は分からないことを詳しく教えてくださり、一緒に考えてくれる先輩の方々をとても頼りにしています。
いずれは、自分が専門学校で学んだプログラミングの技術を生かして、地理情報システムのアップデートや管理といった仕事にも携わっていきたいと思っています。業務に必要な情報処理や測量士の上級資格の取得にもチャレンジしていくつもりです。

好きな土木の仕事で、
地元長野県に貢献できる
よろこび
T.Dさん
調査設計部 調査設計課
入社して13年目になります。測量の業務を経て、現在は調査設計部で長野県の土木設計関連の業務に携わっています。私は主に砂防施設や河川の調査設計を担当し、砂防堰堤や河川護岸の設計をしています。部では他にも、下水、道路の設計なども手がけています。
仕事の流れとしては、まずは県から発注を受けて現場の調査を行い、その場所に必要な施設を検討します。測量、地質調査などのデータをいただいて施設の図面を作り、工事に必要な資材等の数量の計算なども行います。
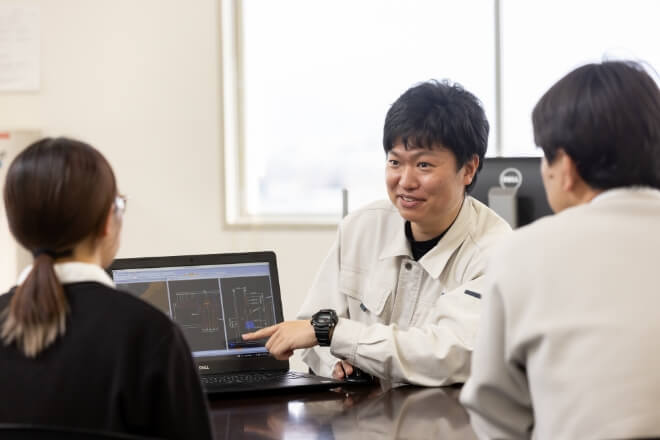
砂防堰堤というのは、人が住む場所に土砂が流れ出ることを防ぐためのダムのようなもので、山の中に高さ10メートル、横幅40メートルといった巨大な施設を建設することになります。自分が設計したものが完成し、最初に現場で目にした時は感慨深いものがありました。
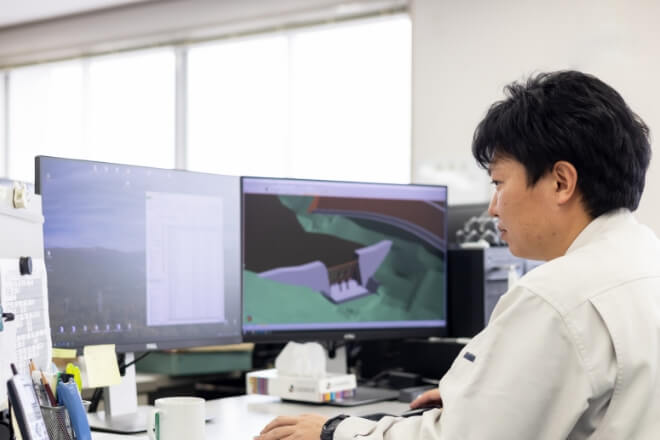
私の実家は長野県内で測量関係の事業をしていて、子どものころから測量や土木が身近にありました。親が言うには、ショベルカーなどの建機が好きで、工事現場を飽きもせずに眺めていた子どもだったそうです。
測量が学べるということで長野高専(国立高等専門学校機構 長野工業高等専門学校)に進学しました。興味のある土木について知ることができ、勉強がとても楽しかったです。
卒業後は県内企業に就職して、地元長野県に貢献したいという思いがありました。非常勤講師に協同測量社の社員がいたことで縁があり、インターンシップに参加して、若い社員が活躍している姿に魅力を感じて入社しました。
調査設計の仕事は10年目になります。資格がないとできない仕事もあるので、今後は部の先輩方と遜色ない資格を取得していきたいです。たとえば、技術士は一定期間の実務経験が要求され、基本的な知識を持った上で、問題解決力や課題遂行能力を問われる論文を書くことになります。業務で得た経験が活きてくるので、日々の仕事の中で経験を積み、知識を蓄えていきたいと思っています。

自然を守ることに
つながる、
環境調査に感じる
やりがい
F.Yさん
環境部 環境課
環境部に所属して、猛禽類の調査をはじめ、昆虫類、魚類、植物等の自然環境の調査業務に携わっています。
長野県内で実施する公共事業では、工事着手前から施行中にかけて環境調査を行うケースがあります。調査の結果で、事業実施に伴い生態系への影響が懸念される場合には、保全対策を検討し、提案します。

入社して初めての仕事でもあり、印象に残っているのがサケの遡上調査です。新潟県の海から信濃川を遡上するサケがどこまで遡上しているのか、サケに発信機を付けて行動を調査しました。残念ながら調査は2箇年携わっただけですが、今後も調査ができるといいなと思っています。

猛禽類には個体数が少ない絶滅危惧種に指定されている種があります。生態を調査することが絶滅に瀕する生き物を守るだけではなく、地域の生態系を保全することにもつながります。そのことにやりがいを感じながら、環境調査の仕事をしています。
私は新卒で工業系の会社に就職しましたが、同僚に誘われて浅間山に登ったことがきっかけで、それまで地元でありながら興味のなかった山の自然に心が動き、登山ガイドといったような自然に関わる仕事をしたくなって、自然環境を学べる専門学校に入学しました。学校で学ぶうちに自然環境の調査に興味を持つようになり、協同測量社の環境部の求人募集を見つけました。
協同測量社に入社する前に環境調査のアルバイトをさせてもらったのですが、部長のおおらかな人柄や、自然全般に関する知識が豊富なこと、仕事への姿勢などに触れ、信頼できる人だなと感じて入社を決意しました。
また、先輩社員たちは環境調査のプロです。そういった方々に教わりながら仕事ができることを、とてもありがたく思っています。専門知識を深めながら、業務に必要な技術士等の資格取得にも挑戦していきたいです。

答えのない問いに向き合い
人と自然と街の
ベストな共生圏を探る
O.Nさん
環境部
入社1年目で、今は主に猛禽類の生態把握や保全対策をする環境調査に携わっています。この仕事のおもしろさは、正解がない課題をみんなで突き詰めていくところです。
例えば人間の暮らしを守る砂防ダムの建設は、動物たちの生息地に干渉し、個体数を減少させる要因になりかねません。特に大規模な工事が行われる際、相互にベストなバランスを保てるよう気を配るのが私たちの役目です。スコープや双眼鏡、カメラなどを使ってワシやタカの観察をし、山を歩き回って営巣地を特定する。技術だけでは成立しない、探究しがいのある部署です。

昆虫採集に夢中だった幼少期から、私にとって自然は大好きで身近な存在です。中学卒業後は土木の仕事に興味を持って長野高専(国立高等専門学校機構 長野工業高等専門学校)に進学。設計部署にインターンシップしたのがきっかけで、協同測量社が行う建設コンサルタントという仕事を知りました。

その後は大学院で環境経済学を学びながら環境調査のアルバイトを経験し、改めて「自然とダイレクトに関わる仕事がしたい」と感じたのが就職の決め手です。生活面で住宅手当や奨学金返還支援など、福利厚生が充実しているのも魅力でした。
今は1つ目の大きな目標である「技術士(建設部門 建設環境)」の資格取得を目指して勉強をしています。自然環境のスペシャリストでありながら、社内外の人と対話を重ねて街をつくる仕事。長野県の未来を見据えたより良い提案ができるよう、視野を広く挑戦を続けていきたいです。

自らの仕事が地図となり残る
測量を通じて
地元・長野に貢献したい
T.Rさん
測量部
入社して以来6年、測量部で地籍調査の担当をしています。地籍調査とは、主に法務局に置かれた「公図」と呼ばれる図面を更新する仕事です。
不動産取引や公共事業の実施、また災害時の街の復旧などに欠かせない公図は、現存する図面が明治から大正時代に作られており、登録された情報と現地の状態が合っていない場所が多くあります。

そこで私たちが法務局のデータを元に現地に赴き、地権者と話をしながら、境界の確定や座標の測定、計算など作業を行います。自分の仕事が地図として形になり、誰かの役に立っているという実感が1番のやりがいです。

長野工業高校を卒業後、兄の後を追って新潟工科専門学校へ進学しました。地図を作る仕事に興味を持ったのは、測量科の実習で公園の実測を行ったときです。身近な場所が自らの作業によって形になっていくワクワクは、今も忘れられません。生まれ育った長野県でこの学びを生かしたいと考え、協同測量社を見学、就職を決めました。
測量部では、ドローンなど最新機材の導入が進んでいます。私もドローンを飛ばすための免許を取得し、地籍調査と並行して新たな測量に携わる機会をいただきました。会社には現場からの提案を柔軟に受け入れ、資格取得も積極的に後押ししてくれる風土があります。全国から同業者が集まって行われる勉強会では、同じ仕事に取り組む若手と会えるのが、モチベーションの維持、向上につながっています。
